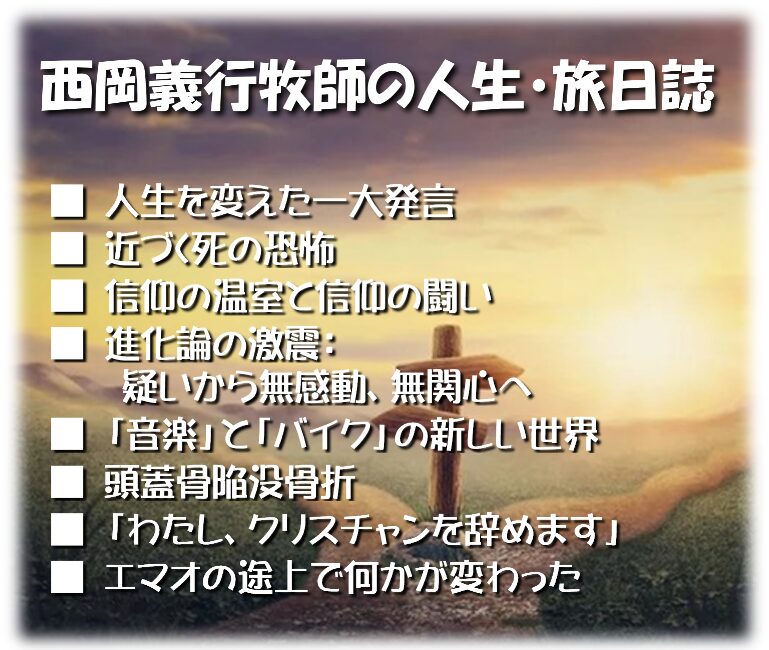
■■■■ 西岡義行牧師の人生・旅日誌 ■■■■
■ 人生を変えた一大発言
今から50年以上も前のことである。日本にビリー・グラハムが来日し、聖書の福音を伝える国際大会が東京で開かれた。このグラハム師は、米国のギャラップの調査によると、毎年のように「尊敬する人ベスト10」に入るほどの人で、二十世紀を代表する伝道者である。アメリカ大統領の個人的カウンセラーとしても用いられつづけ、米国の大統領就任式でも登場するので、少し前まではアメリカでは彼を知らない人はいないと言われたほどである。
そんなことなど何も知らないわたしは、連合聖歌隊の一員であった両親について行った。聖歌隊席横のコンクリートの段に座った。その夜、あの後楽園球場(現在の東京ドーム)にハレルヤ・コーラスが響き渡った。長身の外国人が聖書を片手に持ち上げ、大胆に福音を語り、大勢の人々が、観客席から前のプラットホームに進み出て、ひざまずいて祈る。その光景は、今もわたしの脳裏に焼き付いている。もちろん、五歳児には、実際何が起きていたのか、理解できるはずもない。しかし、その時の深い感動は、わたしを思わぬ行動へと動かしてしまった。それは、その直後の日曜礼拝のあとに起きた。
そのころ家族で通っていた八王子キリスト教会は、まだ会堂を持たず、集まる場所を転々とする小さな群れであった。十数名ほどの礼拝が、忠実屋の寮の食堂で行われていた。礼拝が終わると、何を思ったか、「ボク、大きくなったら日本のビリー・グラハムになる」ということばがわたしの口から出ていった。当時八王子教会に遣わされていた、東京聖書学院の女子寮舎監の中居栄子(旧姓川上)師は、この言葉を神から出たことと思ったのだろう。私を講壇のところに連れて行って、「今言ったことをもう一度話してごらん」と耳打ちした。わたしはオルガンの椅子を持っていき、その上に立った。礼拝後の雑然としていた食堂は沈黙し、わたしの口からもう一度飛び出した。
「ボク、大きくなったら‥‥」
五歳児なら、「大きくなったら、スーパーマンになる」とか、「お嫁サンになる」、「ホームラン王になる」と言っても、笑って終わる。しかし、牧師も教会の皆も、それを主から出たこととし、祈りへと導かれたのだ。ことの重大さも知らずに「アーメン」と言った。しかし、この出来事は、やがてわたしを苦しめることとなった。
■ 近づく死の恐怖
親の職業は子の人生の一部となるのかもしれない。母が家庭保育をしていたことから、我が家は大家族のようだった。看護士の子どもは、夜も預かることが少なくなかった。また、親戚の子も同居していた時期もあり、0歳から5歳の子どもたちに囲まれながら育った。二階に6部屋ある大きな家に増築した中学の頃からは、下宿人も同居していた。その出会いと別れは、人生の一こま一こまを飾っている。
わたしが小学一年生の時に、受け止めきれないショックな出来事が起きた。毎日のように遊んでいたTちゃん(家庭保育で預かっていた2歳の男の子)が、彼の自宅の家庭用洗濯機の渦に飲み込まれ、溺死したのだ。第一発見者はその子の母親だった。近くの病院までその子を抱えて連れて行ったが、手遅れだった。その葬儀に参列したが、お経の響く中、棺にしがみついて泣き崩れる姿は、わたしの心を今も締め付ける。
その翌年、東京聖書学院で開催されたサマーキャンプに参加した。参加できるのは三年生以上ということもあって、宿泊ができない。ところが、当時聖書学院の舎監をされていた恩師、松木牧師宅が聖書学院敷地内にあったことから、そこに泊まって参加できた。先生の書斎に英語の本が沢山あるのを見て驚いたことが昨日のようである。そのキャンプは楽しい思い出であり、また小2のわたしにとって、小さな信仰の決断がなされた。
キャンプからの帰る途中のことだった。西武拝島線に乗り、八高線に乗り換えて八王子に向かった。ジーゼルの匂いのする二両編成の列車の一番前に立っていた私の目に飛び込んできたのは、信じられない光景だった。発進してかなりスピードが上がったとき、突然右の方から自転車らしきものが突っ込んできた。「あッ、危な~い」運転手の叫び声の次の瞬間、小学生が乗る自転車を巻き込むすさまじい音がした。氷つくような恐ろしい瞬間であった。しばらく列車は走り、やっと止まった。何人かは、窓から飛び降り、現場を見に行く。少年と自転車はどうなったのだろう……。
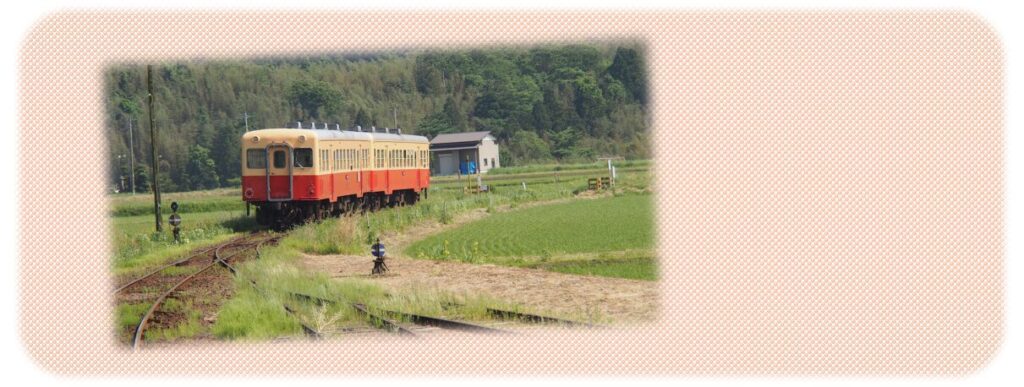
恐ろしくて、体の震えが止まらない。キャンプに行った子どもたちと共に、緊張した時間が過ぎていった。あの瞬間のことが私の中に焼きついてしまった。「生きているって、死んでしまうとは、どんなことなのだろう。」死の恐れが衝撃的な事故に伴って迫ってきた。1968年8月23日のあの瞬間は、今も脳裏から離れない。そして、人身事故で電車が止まるたびに、心の震えを禁じ得ない。そしていのちの問いはわたしを追いかけてくるようになった。
■ 信仰の温室と信仰の闘い
私の家では、信仰は特別なことではなく、生活の一部であった。毎日の聖書を読んで祈る時間は、心のご飯を頂くことで、食事と同じよと言われていた。嫌に思うこともあったが、当然のことと感じることもあった。また、物心つくころから、自宅において「土曜子ども会」が開かれ、近所の子どもたち20名程が集い、共に歌ったり、聖書を学んだり、遊んだりした。土日を含め、毎日が聖書に親しむ生活だった。我が家は、信仰的には温室であった。
その土曜子ども会には、友だちをよく誘ったものだった。自転車で転々としながら遊ぶルートにうまく入れていたのだ。それが自然に出来ていたのだから、今考えても不思議である。中学になると「清川ジュニアクラス」(子ども会の中学生版)も行われた。6時過ぎから開かれていて、クラブ活動が終わってから参加する。そこに来ていた幼馴染が、将来、妹の旦那になるとは、夢にも思わなかった。人生の出会いは、実に不思議なものだ。出会いと言えば、わたしの両親も、教会で出会って結婚した。もし福音が日本に伝わっていなければ、私は存在しないことになる。
さて、野球少年だったわたしは、中学生になり、憧れの野球部に入った。練習を厳しくして、部員の数を減らそうとしていた。1年生部員は、日毎のように減り、気が付くと残ったのは三分の一ほどになっていた。その頃は、背丈はクラスでも平均ほどあり、秋の大会が過ぎると一年生の中でレギュラー争いに入ることが出来た。幸い、なんとかレギュラーの座を奪ったが、日曜にも練習があり、教会をとるか、野球をとるかといった葛藤が始まった。
日曜の練習を休んでも、レギュラーの座もなんとか保つことが出来た。問題は日曜に試合があることだった。牧師と相談した結果、早朝に個人礼拝をしてから、試合に直行することになった。しかし、毎週日曜の練習を休んでいたので、次第にレギュラーの座を確保することが困難になっていった。レギュラーを捨てるか、日曜礼拝を捨てるかの決断を余儀なくされた。そんな中、不思議なことが起きた。それは、中二の後半になり、次期部長を選ぶ時期のことだった。何人かの部長候補の中でいろいろな内輪もめなどもあり、結局わたしが推薦されてしまったのである。
これはチャンスであると感じ、思いきって顧問の先生に申し出た。
「先生、僕は日曜日に教会に行っているので、日曜の練習を午後にしてもらえるのなら、部長を引きうけます。」
なんと、その通りになったのだ。今考えると、数年後のわたしには想像もつかないほど、信仰的な出来事であった。

■ 進化論の激震: 疑いから無感動、無関心へ
信仰は、さまざまな闘いによって守られるが、逆に恵みによって守られていると、内側から崩されていくことが多い。私の場合もそうあった。それは、日曜学校と一般の学校との対立からきていた。日本の教育では、進化論は当然のように教科書に登場してくる。そこにほとんど選択の余地はない。私の心には、不安がよぎったのである。それは、「もしかしたら、この世界が神によって造られたと、本当に信じているのは、このクラスで私一人かもしれない」と。そのことが、試練の時には、問題にはならないのに、とくに試練がないと、疑いへの一歩になっていった。
はたして、聖書あるいは日曜学校の先生が正しいのか、それとも文部省の検定が通った公の教科書が正しいのか。両者が自分の中で対立していった。そして、聖書に信じられない奇跡があるのを見たり、その箇所からのメッセージを聴くたびに、疑いが内側から涌き出てくるのを押さえることが出来ないでいた。疑いと信仰が対立するとき、いとも簡単に信仰が萎えていくのである。
そういえば、エバはあのエデンの園で蛇の誘惑を受けたが、外からの誘惑ではなく、内側にある確信に対して、少しだけノックした程度であった。「園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか」。主が言われたこと、聖書に書かれていることが、「本当にそうなのか」とその心の内にある確信にひとたび触れるだけで、揺れてしまったのである。いきなり不信仰に陥るのではなく、確信の度合いを下げることから、止める事の出来ない不信仰への下り坂へと踏み入れてしまったのかもしれない。「聖書の創世記は本当のことなのだろうか?」と。
高校生になると、いよいよ疑いの思いがサタンによって自分のうちに入っていった。今まで築かれてきた信仰は、その土台から崩れていくようだった。不思議なことに、礼拝は出ているし、聖歌隊にも入っているし、高校の聖書研究会にも入っている。さらに、信じることが出来ない聖書を教える「教会学校の助手」もしていたのである。信じようと努力しても、信仰を努力で立てなおそうとしても、しばらくは続いていも、すぐ息切れしてしまう。
「疑い」は、あらゆることを少しずつ、確実に崩していった。聖書に感動しなくなっていた。本当に、あんな奇跡などあったのだろうか。何百歳も生きたこと、出エジプトの紅海徒渉、主イエスのなさった数々の奇跡、復活、などなど。常識の枠組みが、聖書のメッセージを締め出してしまった。そして、それに関係するいっさいの事に感動を覚えることがなくなった。教会出席は、単なる習慣のひとつとなっていった。そのことが、自分の魂にとって、み言葉がどれだけ大切なことであったかは、次第に分らなくなっていった。でも、それを誰にも言えずにいた。
中学の頃の信仰は、不思議と守られ、クリスマスなどは、クラスの半分ぐらいの友だちを教会のクリスマス会に連れてくるのも、恥ずかしいとは思わなかった。むしろ、人を誘うことに何の戸惑いもなかった。しかし、少しずつ疑いが信仰を浸食していくと、ついに信仰、勉強、クラブ活動、教会生活などが、ばらばらになり、自分が分からなくなり始めていった。そのことに拍車をかける出来事が高校一年のある面接でおきた。
それは、進路を決めるための大切な面接であった。「卒業後は東京聖書学院に入り牧師の道を進みます」と述べると、担任の先生は、「宗教は年を取ってからでも遅くない。自分の人生の可能性を試してからでもいいのでは、」と優しく説得してきた。さらに、「この高校の名誉のためにも、あなたのためにも、最難関の大学を受験してみないか」というのである。その瞬間、「わたしは学校のモルモットではない」と思い、その勧めを拒絶した。あの日、勢いで学院に入り牧師の道を歩むとは言ったものの、その時の先生の言葉が次第に説得力を持ち始めていった。
考えてみれば、その時のわたしは、甲子園を目指す野球部に入っており、同時に生徒会の副会長をしていた。同じ野球部員の中に生徒会長がいたこともあって、次ぎの会長は、誰になるかある意味では決まっていたような状況があった。であるが故に、教師としても自然に力が入ったのも無理はない。しかし、あの面接以来、勉強への意欲は失われた。さらに、高校の校庭が狭かったゆえに、野球部での練習ボールで事故がおき、軟式野球に変えられ、甲子園の夢は消えてしまったのである。生徒会も、甲子園も、勉強も、信仰も、あらゆる事が一気に崩れていったのである。
■「音楽」と「バイク」の新しい世界
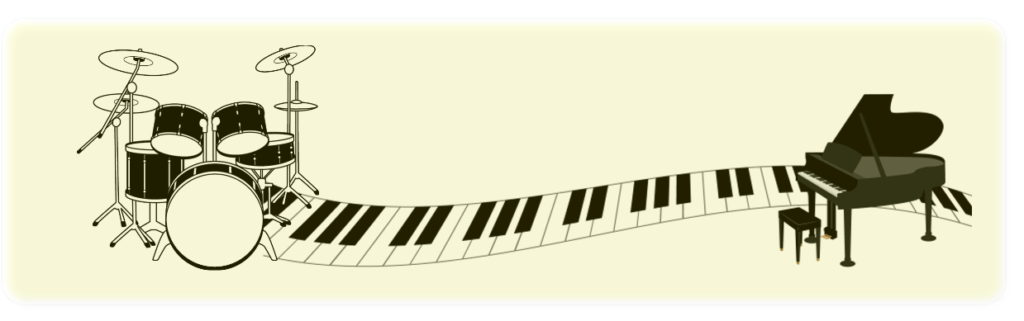
ある日のこと、友人の家に遊びに行き、複雑な事情で悩むその友だちにとっては音楽が大きな支えであることを知った。次第に音楽を介在した様々な関係が広がっていった。生徒会などの関係とは違った新しい世界を感じた。そのうち、わたしが教会などでピアノの奉仕をしていることが知れて、ロックバンドへの誘いを受けた。人は挫折と見るかもしれないが、自分にとっては、新しい世界が開かれたような気がした。それまでは、言わば「良い子」と評されていたが、勉強以外のもの、特に遊ぶことに自由になっていった。
もちろん、バンドへの誘いを断る理由は、忙しいという事のほかはなかった。気がつくと、三つのバンドに入っていた。学校、野球部、生徒会、聖書研究会、教会……本当に忙しくなった。さらにスタジオ代が高く、バイトをしなくてはならない。家庭教師をはじめると、何人からか依頼を受け、さらに忙しくなっていった。バンドはわたしの生活をその根底から変えてしまった。
疲れきっていたわたしには、礼拝は睡魔との闘いとなっていった。礼拝が次第に苦痛となった。聖書の言葉が真剣な祈りをもって語られているのにもかかわらず、わたしの側では、心そこにあらずといった具合で、まさに霊的飢餓状態だった。優先順位が全く崩れてしまい、勉強も、信仰的なことも、ほとんど最後になってしまう。心が亡びること、それが「忙しい」と言われるが、まさにその通りだった。ちょうどコマが回っていないと倒れてしまうように、忙しくしていなければ、立っていられなくなる。立ち止まってじっくり自分の人生のことを考えはじめると、自分を支えられなくなる。「あの幼少時の一言で、自分の人生が決められていいのだろうか。」「死んだら終わりではないか」「今まで信じていたものは、嘘だったのだろうか。」さらに「宗教は、年を取ってからでも…」と言われた担任の先生の言葉が、わたしを揺さぶり始める。音楽は、自分の悩みを忘れさせてはくれた。しかし、何の答えも与えてはくれなかった。
そんな頃、中学の友人が真夜中になると、400ccの改造バイクでやってくる。二階の私の窓に小石をぶつけ、「来いよ」と手招きする。家庭教師をして受験の手助けをしたことのお礼なのかもしれないが、結局付き合うことになった。マフラーを取ったバイクのエンジン音はすさまじく、手で押して家から離れたところで、エンジンをかけた。静かな住宅の30キロ道路を、100キロ近くのスピードで爆音とともに走り抜ける爽快感は、実に近所迷惑そのものであった。バンドの友人たちとも真夜中のドライブで海や山に行ったりもした。
最近はかなり少なくなったとはいえ、時折真夜中爆音をまき散らして川越の田んぼ道を滑走するバイクが通る。そのたびに、子どもたちに誤ったりする。「ごめんね、お父さんも同じことをしていたんだ」と。

本当は死ぬのが恐ろしかったはずだ。しかし、その恐怖をスリルにすり替える見えざる魔力に誘われるまま、闇夜を爆走した。時がたって、両親にその頃のことを聞くと、「夜のバイクのことは分かってたわよ。半分あきらめてたわね…」と言われた。祈るしかなかったのかもしれない。その頃の私はどうにかなっていた。中学の別の友人がバイクで命を落としたと知っても、止められなかった。しかし、付きまとう「生とは?死とは?」の問いから逃げることはできないでいた。
■ 頭蓋骨陥没骨折
高二の二学期は、文化祭などもあって、バンドを三つも掛け持っていたわたしには、殺人的な忙しさであった。信仰的に命を失ったような状況であっても、木曜の祈祷会と土曜学校の多少の手伝い、そして、日曜の教会学校の助手、聖歌隊などの教会の奉仕も続けていたのだ。あらゆる係わりに忙殺されるような日々の中で、全てを投げ出したい、と思うことがあった。全てがいつ崩れてもおかしくないほどであった。そんな時だった。以前から頭痛があったが、ある日突然倒れた。
原因不明の頭痛は、わたしを悩ませていた。子どもの頃から、右側の上頭部が時として痛みに襲われていた。歯医者以外に、行くのが恐ろしいと思う場所があった。床屋さんである。それは、痛い上頭部を情け容赦なく洗うからだ。普通に触っても痛いときは痛い。医者嫌いのわたしは、誰にも言わずにいた。しかし、ついに医者に行くことになった。八王子にある近くの病院では原因がわからず、脳外科の名医のいる横浜市立病院に入院することとなった。
何度もCTスキャン等で頭蓋骨を検査した。その断層撮影などで、自分の姿を見た時は、これが自分かと思い、何ともいえない気分になった。確かに右上頭部が陥没しているのだ。しかし、それがどうしてそうなっているのか不明だった。様々な検査の結果、いくつかの可能性が浮上し、難病の可能性すらあがったらしい。痛みが来ない様に処置されたのだろうか。比較的安定している。しかし、親には、家族親戚一同を呼ぶようにという指示が下った。同じ病室には、脳の難病の小学生、交通事故で包帯に包まれた人、脳腫瘍で全身麻痺した人が身を横たえている。変わり果てたその人を見舞う婚約者の姿が痛々しかった。そんな中、わたしの心に様々な思いが交錯した。もしかすると、大変な事になってしまったのかもしれない。
いよいよ手術となった。遠く彼方にあった死の恐怖が忍び寄ってくる。手術前の家族のただならぬ雰囲気に、言いようのない死の恐怖が忍び寄ってきた。強風の中、柵のない高層ビルの屋上で、足がすくむような感覚であった。
そういう時だけは、なぜか自分を造られ た神の存在を否定できない。その存在をみとめることだけが、自分を安定させていた様に思われてならない。いよいよ覚悟を決めて、手術へと向かった。
手術は無事に終わった。結局、難病ではなく、頭蓋骨陥没骨折であった。本当なら、死ぬかあるいは半身不随になるところであったが、わたしの脳皮(頭蓋骨の内側で脳を包む膜)の厚さが普通の人の倍あったことで、骨折していても守られたのだ、と聞かされた。そう言えば小学生の時、誰もいない体育館の倉庫でわたしが倒れていたのを発見されたことがあった。わたしには記憶がないが、その頃からあの頭痛は続いていたのだ。バイクなどの事故で死ぬ前に、激しい頭痛で倒れさせ、わたしを病院に追い込んだ「何らかの背後の存在」を、もはや否定できなくなっていた。
病院で経験した、身の置き場のないような死の恐怖は、自分を越えた何らかの存在なしではいられなくした。手術の前に医者からこのように言われた。
「脳は神の領域なので、よほどのことがない限り手術はしないのだよ。」
当時のわたしには、医者が「神」という言葉を使ったことにある種の衝撃を受けた。自分を越えた存在があり、同時に自分という存在がいつかは死を迎える弱い者であることを否定することはできなくなっていた。
しかし、どうしても分からないことがあった。神の存在は認めたとしても、それがどうして子どもの頃から聞かされていたあの聖書の神なのか。イエス・キリストは本当に神なのだろうか。退院し、また何事もないように生活が戻ってしまったことがむしろ苦しかった。教会では教会学校の手伝いをしていた。場合によっては分級でお話ししなくてはならない。確信のないわたしが「信じることの出来ない聖書」を教えなければならない。自分に偽ることが出来ない。かといって、いまさら献身を取り消すのも苦しい。
この献身自体、物心つかない幼少時の発言に基づいている。自分の人生をそんなあやふやな時期の発言によって決めてしまうことには耐えられない。ついにわたしは一つの大きな決断を下した。自分の本当の気持ちに正直になり、それを牧師にぶつけることだった。退院後、数ケ月したある日の夜のことであった。
■ 「わたし、クリスチャンを辞めます」
ついに、その日がきた。高校三年にもうすぐなろうとする春のことであった。ここで進路を全く転換することで、自分が新しい旅に出られると思っていた。誰にも言わず、いきなり牧師館の玄関でベルをならした。「先生、大事な話があります。」
松木祐三牧師も何事かと思われたであろう。わたしを畳の部屋に招き入れ、ストーブに火を付ける。従子先生(牧師夫人)は、二階から降りてきて、紅茶とケーキを持ってきて「ゆっくりしていってね」と迎えてくれる。わたしはその夜、こう申し上げた。
「先生、信仰が分からなくなりました。神を信じるとしても、それがイエス・キリストの神であるということに確信をもてないのに、そのことに献身することは出来ません。献身も、クリスチャンであることも、いっさい取りやめます。信じるとしても、他の宗教をこの目で見て、どの神が本当なのか確かめてから、もし最後にキリストの神が本当であると分かったら、それから教会に戻ってきます。」
それから闘いが始まった。今まで、聞きたくても聞けなかった様々な疑問が次々とわたしの口から出てきた。本当に聖書に記されている奇跡はあったのだろうか。盲人の目が瞬時に開いたり、水がぶどう酒になったり、湖の上を歩いたり、完全に死んだ者が復活したり、などなど。教育を受けたこの大の大人が、一つ一つ本当に信じた上で説教しているのか、問い正したかった。本質を問えば、うろたえるだろうと不遜にも思っていたのかもしれない。そしてついに牧師の目を睨め付けて問い詰めてしまった。
「先生は、あんな奇跡を本当に信じた上で語っているんですか」。
だからこそ驚いた。松木牧師はうろたえず、懇切丁寧に一つ一つの問いに答えてくださったのだ。しかも、その日から毎晩のように、「まだまだあるでしょう?」とすべての疑問に付き合うつもりで、私に尋ねられたのだ。来る日も来る日も、真夜中まで語り合った。「信じられないこと」「聖書や信仰に関するあの疑問、この疑問」。創世記から始まり、海が分かれてエジプトを出たこと、様々な奇跡、復活や黙示録、さらに十字軍から最近の進化論に至るまで、ありったけの疑問をぶつけまくった。
松木先生は、「そのような疑問は何もわたしがはじめて持っているのではなく、今まで多くの人々が悩んみ、様々な答えを見出してきているのだよ」と丁寧に説明された。また、疑問に向き合ってきた歴史をも紐解いてくださった。その説明が全て分ったわけではなかった。けれども、疑っている自分の小ささを知らされたような気がした。
このような奇跡への問いは、現在も完全に理性的に解決したとはいいがたい。ただ、理性で解決できる領域に神を閉じ込めることが出来るほど、「大自然やわたしという存在を創造された神」は小さくはないということをどこかで感じていた。手術前後の小さな信仰が息を吹き返したのかもしれない。疑問を全て出し切ってしまうと、結局小さな弱い自分がぽつんと残ったようだった。
途方に暮れていると、松木先生は「聖書の奇跡を信じるという特別な信仰がなければ救われない、などと聖書には書いてないよ」と述べられた。「神から離れた罪人に近づいて、その罪の裁きを受けて神の前に立つことが出来るように、十字架にかかって下さったこの福音は、ただ幼子のように受け取るだけでいいのだ。それ以外の道はとざされたのだよ。それが主のお心なのだよ」と。

■ エマオの途上で何かが変わった
ルカ伝24章に、十字架でイエスが死なれたあと、失意の中、エルサレムを背にしてとぼとぼと歩いていた二人の弟子が登場する。今まで信じていた方が、ローマ軍によって処刑され、しかもその死体すらなくなっている。それまで素朴に信じてきた者にとって、大きな力ある何ものかによってその信仰を奪われたような状況であった。
わたしも、教会から背を向けて歩き始めていた。近代化し、世俗化した何らかの力によって、信仰が奪われ、死んだような状態であった。よの多くの人々はイエスのことなど信じてはいないし、自分も信じられない。今まで信じてきたことに裏切られたような失意の中で、近くにおられる誰かに、必死で訴えていたのだ。
ところが、わたしの横に「イエスは生きておられる」(v23)などと言う人がいるのだ。そのことすら不思議にうつる。しかし、今になって思うと、毎晩のように牧師宅に通い、自分の疑問をぶつけていた時、わたしの横に主がおられることに気が付かなかったのは、ルカ24章16節にある言葉と同じであろう。「目がさえぎられて、イエスを認めることができなかった」(16節)のだ。
疑問が解けるまでとことん話そうと思っていた。結局、毎晩のように夜12時過ぎまで話し込んでしまった。信じられない聖書の箇所を一緒に開き、そこから丁寧にその意味を語ってくださった。今考えると、毎晩おそくまで、よくも付き合ってくださったものだと思う。何も分かっていなかったわたしを包んで聞いてくださり、祈ってくださっていたのだ。
わたしもわたしで、よくもあそこまで反抗的に、かつ率直に本音を言えたものだ。「献身者」であるというレッテルを剥ぎ取り、疑い深き、ただの存在となると、自由になれる。何を言ってもどんな質問をしても、「ここまで開き直ってしまったのだから、かまわない」と思った。そのような状況は、むしろわたしの心を素直にしていた。そして聖書の言葉がこちらが困ってしまうほど自分の心に入ってきてしまう。あのエマオの途上の二人の弟子が、「道々お話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が内に燃えたではないか」と振り返っているが、不思議なほど似通っている。きっと、祈られていたのであろう。そして、あの場にもう一人おられたの であろう。復活の主が。
何日も通う中、わたしの心に変化がおき始めていた。松木先生が、「ちょうど聖書学院で春の聖会があるから、出席したらいいよ」と勧めて下さった。自分が主を信じたあのチャペルにもう一度帰って、一から出直しだと思った。
説教者が誰であるかは、全く覚えていない。ただ、かつて信じていたもの、そして裏切られたと思っていたもの、自分が反抗しつつも、結局反抗すればするほど揺らぐことのない大きな存在の前に、自分の小ささを感じていた。自分の人生を決めるのは、自分なのだろうか。ちょっとしたことで、命などなくなるような小さな存在。事実その小ささを死の恐怖とともにどこかで知ってしまった。自分を創造された存在がこの聖書の神であると受け入れることが、あまりにも自然な結論であり、それ以外の選択は色あせていた。
集会の終わりに、招きがあった。「あなたの人生を主の御用にささげる人はいませんか。」それは、もはや説教者の言葉ではなかった。ずっとわたしの魂に響きつづけてきた神の言葉であった。前に出て、ひざまずいたとき、戻るべきところに戻ったと実感した。不思議な聖なる存在の前に、今までのことが一つになっていった。
わたしの心の変化は、説明がつかない。確かに、聖書にもなぜあのザアカイの心が変化したか、モーセの心が、パウロの心が変化したか、分かるようでわからない。状況はわかるが、納得のゆく内的変化の説明が欠けている。そのことが、今となってはなぜか嬉しく思う。語れないことがある。言葉にならないことがある。それと真剣に向き合うが、どうしても言葉が見つからない。そういう次元の変化が、わたしの身に起きたことは、わたしの計画でも、努力でも、願いでも、決意でもない。ただ、神のあわれみなのだとしか言えない。罪深い私たちのところに来られ、罪をゆるし、迎えてくださるという、聖書のメッセージがわたしの身に起き、それを表現する言葉を持ち合わせていないから、それが賛美や行動に変わるのかもしれない。
「あなたがたの救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。」(エペソ2:8~9)
今わたしは、牧師となって一人ひとりの人生と向き合っている。不思議な出会いがいくつもある。それも、きっと神が導かれているのだと信じている。その人の中できっと神が御業をなさるに違いないと、信じているからだ。わたしが変えられた時がそうだったように。
--------------------------------------- つづく
